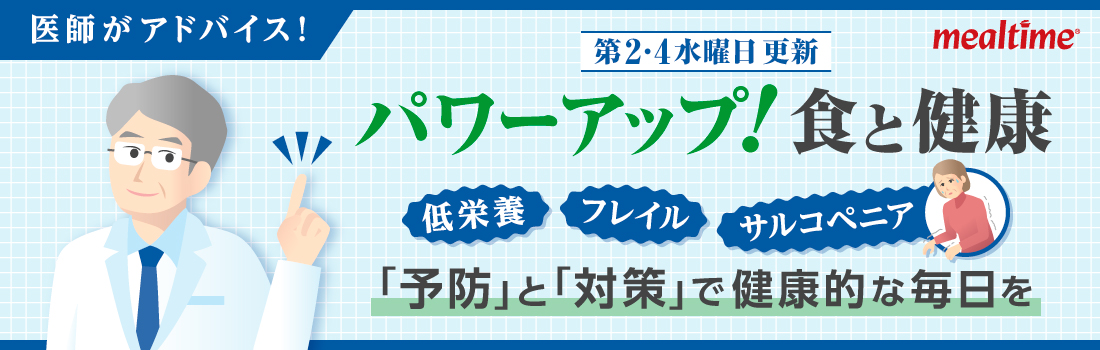サルコペニア肥満という身体組成の変化(今村 也寸志)
年齢と共に現れる変化
年齢とともに手足は細くなるのにお腹は出てきます。誰にでも見られる加齢に伴う体型の変化です。しかし、これはサルコペニア肥満(サルコペニア+内臓肥満)と呼ばれる病的状態と地続きの変化であり、その間に明確な境界線がありません。
サルコペニアとは加齢に伴う筋肉量の減少(筋力の低下)を指します。大抵の人は30歳を過ぎると筋肉量(筋力)の減少が始まります。高齢になると、ペットボトルのフタが開けにくい、立ち上がるのに苦労する、やがて歩行にも難渋するようになります。しかも、筋肉の中でも速筋と呼ばれる瞬発力を発揮する筋肉の減少が優先します。速筋は躓いた時に素早く体制を立て直すのに重要な筋肉ですから、思いのほか転倒しやすい体になっているのです。また、歳とともに骨は脆くなりますから、転倒による骨折のリスクも高まります。
年齢と共に脂肪の蓄積場所が変わる
一方、筋肉量が減少するのと反対に、体脂肪量(率)は増加します。さらに、その脂肪の蓄積場所は皮下脂肪から内臓脂肪にシフトします。この原因の一つが、加齢に伴う脂肪細胞の機能低下です。
人は余分な栄養を脂肪組織に貯蔵します。まず皮下脂肪組織に貯められ、そこが満杯になると、余剰分が内臓脂肪組織に送られます1)。老化や代謝異常などに伴って皮下脂肪細胞の貯蔵能力が低下すると、貯蔵できる脂肪の量が減ります(手足とおなか周りを比べると、手足の皮下脂肪細胞の変化が早い)。このため、内臓脂肪組織に向かう分が増えることになります。内臓脂肪細胞は力が落ちていても、数が多いため、全体として大量の栄養を貯め込むことが可能です。若い時は皮下脂肪が全身に分布しているため、“ぽっちゃり”としていますが、中年以降には手足の皮下脂肪が減り、脂肪はおなか周りの皮下脂肪組織や内臓脂肪組織に集中します。さらに高齢になると、胸やおなかの皮下脂肪も減少し、ますます内臓脂肪が増えていくことになります。
このように、加齢に伴う身体組成の変化は、サルコペニアと内臓肥満という一見相反する健康リスクを同時に抱えることにつながります。それでは、どのような対策が求められるのでしょうか。
サルコペニア肥満対策に重要な三つの柱
まず注意すべきは、身体組成の変化により健康と体型の関係が変化するという事実です。一般に、「BMI 22 kg/m2が標準体重」とされ、生活習慣病予防などの目安です。しかし、高齢者の総死亡リスクや健康リスクの観点からは、BMI 21.5〜25.0 kg/m²が適切とする報告が多くみられます2)。例えば、日本の代表的な疫学研究である「NIPPON DATA80」(65歳以上の日本人を対象)は、23.0〜24.9 kg/m2を最も死亡率の低いBMIと報告しています3)。筋肉の維持のためには、ある程度の体重が必要であり、やせ過ぎは健康にとってリスクであることを示唆しています。
サルコペニア肥満対策のひとつは栄養です。体重を維持するために必要なエネルギー(カロリー)量の食事をとる必要があります。また、筋肉の維持・増強のためには、十分なたんぱく質摂取(高齢者では体重1kgあたり1.2〜1.5 g)が推奨されます。しかし、高齢者では食欲の低下や慢性疾患の影響により、十分な栄養摂取は困難な場合があります。栄養価の高い食事の提供や間食・補助食品の活用などの工夫が必要です。また、それらを可能とする生活支援体制の整備も不可欠です。
運動は筋肉の維持・増強と脂肪の燃焼に重要です。しかも筋肉や脂肪組織の老化・機能低下を遅延させる効果も報告されています4)。運動には様々な種類があり、それぞれに優れた点がありますが、取り組みやすい運動としてはウォーキングが挙げられます。ウォーキングは、筋力や有酸素運動機能、バランス能力の強化に効果的な総合的な運動です。「さっさか歩き(速歩)」と疲れたら「ゆっくり歩き」を繰り返すインターバル速歩が推奨されます。また、歩行時のかかとへの刺激は骨形成を促し、日光を浴びることでビタミンDの活性化にもつながります。
栄養と運動に加えて、「人との交流」も非常に重要です5)。社会的フレイル(社会的孤独や交流の減少など)は、身体的フレイルや認知機能の低下の引き金になるからです。たとえば、歩行中に話しかけられると立ち止まってしまう高齢者(“Stop walking when talking” 現象)は、転倒のリスクが高いと言われます。これは、二つのことを同時に行う能力(認知能力のひとつ)の低下と運動機能の低下が関連することを示しています。こういった状況を避けるためにも、日頃から友人と連れ立って、ウォーキングと会話を楽しむことは大切なのです。
栄養と運動、そして人・社会との交流(意欲の維持・認知症予防・社会資源の活用など)はサルコペニア肥満対策の三つの柱で、どれひとつとして欠かすことはできないのです。

(参考)
1)Tchernof PA and Després JP、Physiol Rev 2013
2)健康日本21(第二次)(https://www.mhlw.go.jp/)
3)Okamura T, et al. J Epidemiol. 2015.
4)Jia D. et al. Metabolites 2024
5)竹内寛貴ら、日本公衆衛生雑誌 2023
自己紹介
肝臓病専門医です。肝臓病の中でも肝不全や肝がんの臨床を中心にしてきましたが、最近では脂肪性肝疾患や糖尿病の患者の診療が増えています。
患者さんとどのように接しているか
病気は患者自身の問題です。患者さんが自分の病気を理解し、自分で考えることができる、その一助になることが出来ればと考えています。
経歴
鹿児島大学医学部大学院(生化学)卒。医学博士。
現在、鹿児島厚生連病院 肝臓内科勤務。
日本消化器病学会(指導医・専門医)、日本肝臓学会(専門医)、日本糖尿病学会、日本栄養治療学会(専門医)、日本病態栄養学会などに参加しています。
好きな言葉
Stay hungry, stay foolish.(サルコペニアの元凶かもしれませんが、・・・)
ミールタイム パワーアップ食の活用方法
質の良い栄養と食の喜びを提供する生活支援の一つと考えます。