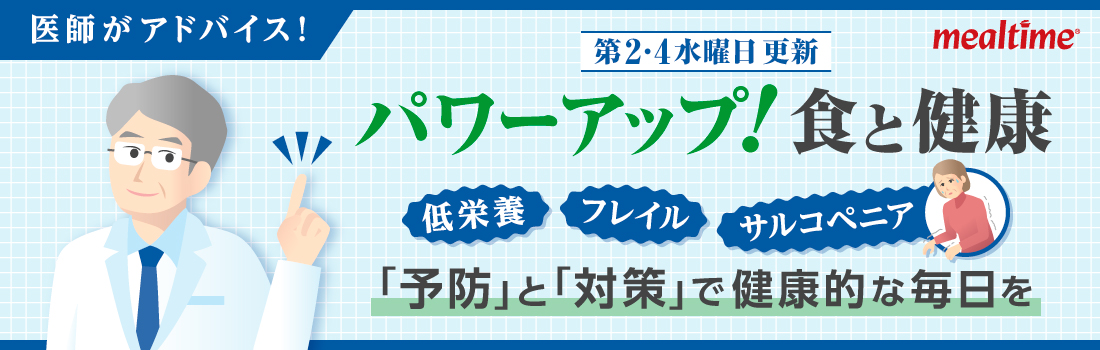腎臓が悪いと野菜や果物を食べてはダメなの!?(細島 康宏)
腎臓病があると野菜や果物を食べてはいけないと聞いたことはありませんか?もしかしたら、すでにそのような食事を実践されている患者さんもいらっしゃるかもしれません。本当にそうなのでしょうか?近年、慢性腎臓病に対する野菜や果物の摂取についての考え方が少し変わってきていますので、そのことについて説明させてもらいたいと思います。
1.腎臓が悪いと野菜や果物を食べてはいけないの?
野菜や果物はビタミンやミネラル、食物繊維が豊富なものが多く、我々の健康的な食生活を考える場合においてとても重要なものです。しかし、ミネラルの1つであるカリウムをたくさん含んでいるものが多いことも事実です。これまでに慢性腎臓病患者さんには、高カリウム血症の予防やその管理のために、食事において野菜や果物を制限することが慣習的に行われてきました(水にさらすことや茹でこぼすことで、カリウムを減らして食べることをお勧めすることもありました)。それは、著明な高カリウム血症は不整脈など重篤な病態を引き起こすことがあるからです。
一方で、近年、血清カリウム値の管理において、食事からのカリウム摂取量を制限する根拠に乏しいかもしれないとする報告があることや、高カリウム血症がない場合に野菜や果物の制限を行うことで、健康に有益であることが期待される栄養素が得られない可能性があるという意見も出て来ています。すなわち、慢性腎臓病に対する野菜や果物の摂取についての再考がなされているということです。
2.慢性腎臓病患者さんにおいて野菜や果物を食べる食事療法も提案されています!
近年、この分野において注目されていることの1つに、野菜や果物には体内の酸産生量(食事性酸負荷)を軽減させる可能性があるということがあります。食事性酸負荷という言葉を聞きなれない方もいらっしゃるかもしれませんが、食品には肉などの酸性食品と、野菜や果物などのアルカリ性食品があり、食事において酸性のものを多く摂りすぎると様々な病気を引き起こしてしまう可能性が報告されています(図)。

そういった中で、日本腎臓学会による「エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン2023」では、「代謝性アシドーシス(身体が酸性に傾く状態)を有する慢性腎臓病の患者さんでは、内因性酸産生量を抑制し、腎機能悪化を抑制する可能性があることから、アルカリ性食品(野菜や果物の摂取など)による食事療法を提案する」ことが記されています。
実際の臨床の場におけるカリウム管理においては、一律に野菜や果物の摂取制限を行うのではなく、食事調査や蓄尿検査を積極的に行うことでその摂取量を確認することをはじめ、排便のコントロールや、血清カリウム値に関連し得る薬剤の使用について、医師や管理栄養士により確認、調整していくことも重要であると考えられます。もちろん、野菜や果物の摂取制限が必要とされる場合もありますが、一人ひとりの患者さんに適切なそれらの摂取を一緒に考えていく必要性を強調したいと思います。
3.野菜や果物を摂取すると筋肉量や筋力がアップする!?
以前から、身体が酸性に傾く状態である代謝性アシドーシスがあると筋肉の合成と分解のバランスが崩れてしまうことが知られています。すなわち、そのような状態では筋肉量や筋力が減少してしまう可能性があるということです。そして、これまでの多くの研究結果をまとめた検討で、その代謝性アシドーシスを治療することで筋肉量や筋力が改善することも報告されています。これらの結果からは、野菜や果物も含めたバランスのよい食事は、代謝性アシドーシスの改善につながり、筋肉にも良い効果を与える可能性があるということと考えられます。
まとめ
慢性腎臓病の食事療法において重要なことは、一律に制限することだけを考えるのではなく、患者さん個々の状態を把握しながら、柔軟にその内容を検討することです。そして、それらが患者さんにとって正しい選択となっているかの確認を行いながら、患者さんと医師や管理栄養士をはじめとした多職種で連携し、適宜、見直しを行っていくことだと考えられます。このことは、野菜や果物の摂取についても当てはまり、「腎臓が悪いと野菜や果物を食べては絶対にダメ」ということではないと理解できます。是非、一度、主治医の先生や管理栄養士さんと相談してみてもらえればと思います。
筆者
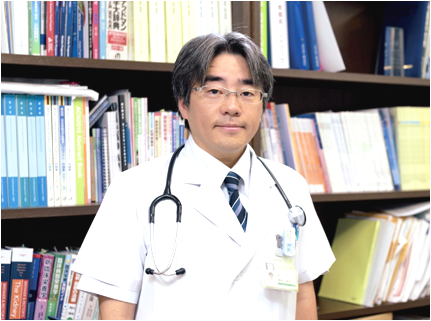
腎研究センター(トランスレーショナルリサーチ部門)病態栄養学講座
特任准教授 細島 康宏
自己紹介
石川県内灘町の出身です。新潟大学の医学部を卒業後、新潟県内の各病院にて臨床業務に従事してきました。2014年より、現職である新潟大学の病態栄養学講座(寄附講座、現在は共同研究講座に移行)の特任准教授を務めています。食事や栄養に関して、県内外を問わず多数の講演会や市民公開講座などでお話をさせて頂いております。内科総合専門医、腎臓専門医、透析専門医です。
患者様とどのように接しているか
私は患者さんとコミュニケーションをとることがとても好きなので、医療のことだけでなく趣味や時事ネタやご家族のことなど、いろいろとお話をさせて頂いています。例えば外来であれば、今日この外来に来て安心した、ためになったなど、患者さん方が「来てよかった」と思ってもらえるように努力しています。
経歴
【学歴】
2002年:新潟大学医学部卒
2009年:新潟大学大学院医歯学総合研究科博士課程修了(博士(医学)取得)
【職歴】
2012年:新潟大学農学部 農水省委託医農連携プロジェクト特任助教
2014年:新潟大学大学院医歯学総合研究科 病態栄養学講座 特任准教授
2016年:新潟大学大学院医歯学総合研究科 腎研究センター(トランスレーショナルリサーチ部門)病態栄養学講座 特任准教授(現職)
好きな言葉
諦めないのが 僕らの道標(GReeeeNの楽曲「Green Boys」の歌詞の一部です)
ミールタイム パワーアップ食の活用方法
バリエーションが豊富ですので、楽しみながら食事療法を継続してください。